赤ちゃんのお世話に欠かせない哺乳瓶。授乳に便利で頼りになる存在ですが、実は長く使い続けることで、歯並びの乱れや虫歯のリスクを高めてしまうことをご存知ですか?
「哺乳瓶はいつまで使っていいの?」「やめ時がわからない」「卒業させたいけど泣いてしまう」——そんな保護者の疑問や不安に応えるべく、本記事では哺乳瓶と口腔の発達の関係、卒業の適切なタイミングや進め方を、データとともにわかりやすく解説します。
目次
哺乳瓶の役割と乳児期の歯の発達

生後すぐの赤ちゃんにとって、哺乳瓶は栄養摂取と吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)を育てる重要なツールです。しかし、歯の萌出(生え始め)や顎の成長が進むと、哺乳瓶が発達の妨げになる可能性が出てきます。
日本小児歯科学会によると、赤ちゃんの歯は生後6か月頃から徐々に生え始め、1歳半頃には約16本、2歳半で20本の乳歯が完成します。つまり、この時期からは「噛む力」や「舌の使い方」など、口の機能を鍛える時期に入るのです。
哺乳瓶の長期使用が招く3つのリスク

哺乳瓶を1歳半~2歳以降も使用し続けると、以下のようなリスクが指摘されています。
歯並びへの影響(出っ歯・開咬)
長期間の哺乳瓶吸引により、上の前歯が前方に押し出され、出っ歯(上顎前突)や前歯が噛み合わない開咬の原因になることがあります。特に寝ながらの吸引は顕著です。
| 症状 | 説明 |
| 出っ歯 | 哺乳瓶の乳首が前歯を常に押すことで、上顎が前方に成長 |
| 開咬 | 口を閉じても前歯が接触せず、発音や咀嚼に影響が出る |
虫歯のリスク増加
哺乳瓶で甘い飲み物(ミルク、果汁、乳酸菌飲料など)を頻繁に与えると、“哺乳瓶う蝕”と呼ばれる前歯の虫歯が発生しやすくなります。特に、寝る前や夜間授乳後の口腔ケアが不十分な場合は危険です。
厚生労働省の調査でも、1歳半〜2歳の虫歯発生率は年々増加傾向にあり、背景には飲み物の内容や授乳習慣が影響していると考えられています。
嚥下・発音・口腔機能の発達遅れ
哺乳瓶を長く使いすぎると、舌の使い方が限定され、正しい嚥下(のみこみ)や発音が身につきにくくなるリスクもあります。スプーン食・コップ飲み・固形食への移行が遅れると、「口呼吸」や「構音障害」の原因にもなります。
哺乳瓶卒業の目安はいつ?
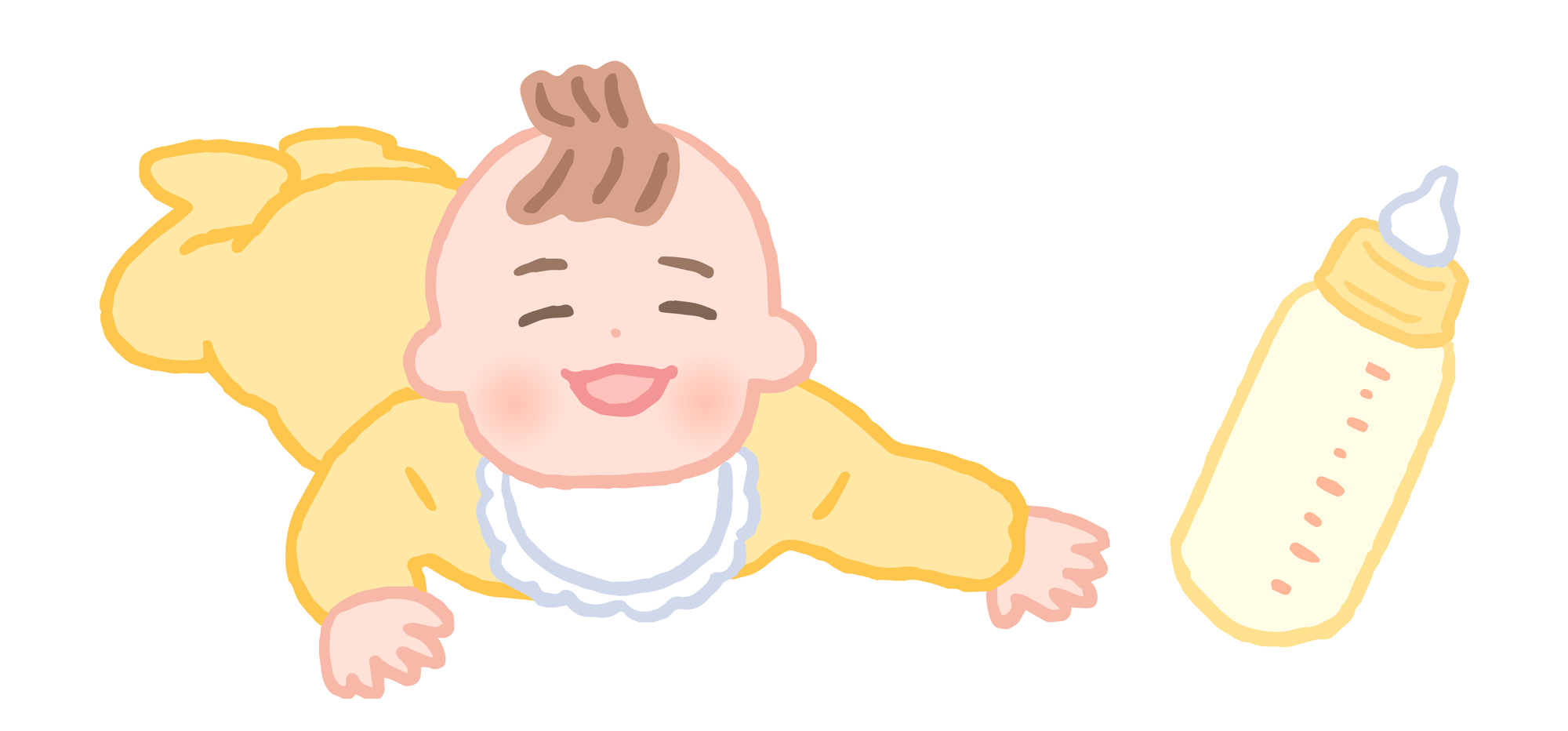
日本小児歯科学会やWHO(世界保健機関)は、哺乳瓶卒業の推奨時期について以下のように示しています。
| 機関 | 推奨時期 |
| 日本小児歯科学会 | 1歳~1歳半を目安にストローマグやコップへの切り替えを推奨 |
| WHO | 生後12か月以降は哺乳瓶の使用を減らすことを推奨 |
また、厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド」(2021年改訂)では、1歳以降はコップ飲みに移行し、哺乳瓶は卒業するよう指導されています。
哺乳瓶卒業のためのステップとコツ

「やめさせたいけど嫌がって泣く」というお悩みも多い哺乳瓶卒業。以下のようなステップで段階的に進めるのがおすすめです。
ステップ1:ストローマグやコップに慣れさせる(9~12か月頃)
・最初はスープや麦茶など、飲みやすい液体を少量から
・お風呂や遊びの時間に楽しくトライする
・哺乳瓶と並行しながら、徐々に回数を増やす
ステップ2:哺乳瓶以外の方法で水分やミルクを与える
・コップやストローでフォローアップミルクを与える
・スプーンや注ぎ口付きのトレーニングカップも活用
ステップ3:寝かしつけ時の哺乳瓶を卒業する
・水やお茶に切り替えたり、授乳ではなく抱っこで安心感を与える
・絵本や子守唄など、他の入眠習慣をつくる
・夜間の虫歯予防には口腔ケアの習慣化も大切
よくある質問(Q&A)

Q. 果汁なら虫歯になりにくい?
A. 一見ヘルシーな果汁ですが、糖分と酸性度が高いため虫歯の原因になりやすいです。1歳以降は「水」や「無糖のお茶」が基本です。
Q. 卒業させるのがかわいそう…
A. 感情的には理解できますが、哺乳瓶を長期使用する方が将来の歯科矯正や虫歯治療でつらい思いをする可能性が高くなります。「今のやさしさ」よりも「将来の健康」を考えて一歩踏み出しましょう。
歯科医院でもできるサポート

哺乳瓶の卒業や歯並びの不安については、小児歯科で早期に相談するのがおすすめです。
- 歯の萌出状況の確認
- 虫歯のリスク診断
- 口腔機能発達(MFT)へのアドバイス
- 卒業タイミングに応じた生活指導
必要であれば、保健師や栄養士とも連携しながら総合的な支援が受けられます。
まとめ:哺乳瓶卒業は、子どもの未来への第一歩

哺乳瓶は赤ちゃんにとって安心の象徴ですが、使い続けることで歯並び・虫歯・口腔機能の発達に悪影響を及ぼす可能性があります。
この記事のまとめ:
- 哺乳瓶の卒業目安は「1歳~1歳半」頃
- 長期使用は「出っ歯・虫歯・発音障害」の原因に
- ステップを踏んだ移行と、親子のスキンシップが大切
- 気になるときは小児歯科へ早めに相談を
迷いながらも、少しずつ哺乳瓶のない生活へ。
その一歩が、お子さんの健やかな未来をつくる大切なスタートになるかもしれません。





