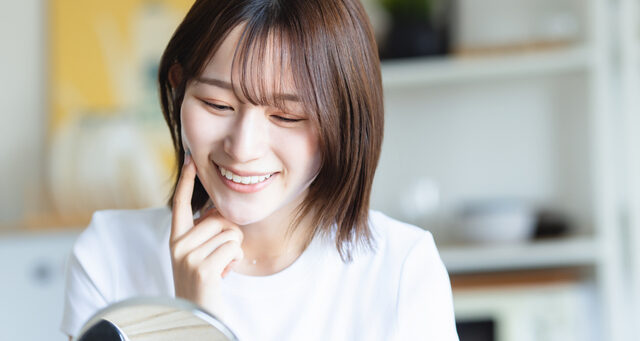「虫歯や口臭予防のために、しっかり磨くのは良いこと」
そう考えて、時間をかけて何度も歯を磨いていませんか?
確かに歯磨きは口腔ケアの基本ですが、“やりすぎ”はかえって歯や歯茎を傷つけ、口内環境を悪化させる原因になることがあります。
実際、日本歯科医師会や日本歯周病学会は「過剰なブラッシングは歯肉退縮や知覚過敏を引き起こす恐れがある」と注意喚起しています。
今回は、歯磨きのしすぎで起こる具体的なトラブルとメカニズム、正しいケアの方法を信頼できるデータと共に解説します。
目次
歯磨きのしすぎで起こる主なトラブル

歯茎下がり(歯肉退縮)
過剰なブラッシング圧や硬い毛の歯ブラシでゴシゴシ磨くと、歯茎が徐々に下がります。
歯茎が下がると本来覆われていた歯根(象牙質)が露出し、虫歯や知覚過敏のリスクが増加します。
歯肉退縮は自然に元には戻らず、進行すると歯周外科治療が必要になるケースもあります。
楔状欠損(くさびじょうけっそん)
歯と歯茎の境目が削れてくさび状に欠ける症状です。
原因は主に「硬い歯ブラシ」「強い圧」「横磨き」の組み合わせ。
欠損部分は象牙質が露出しており、痛みやしみが出やすくなります。
知覚過敏
エナメル質が削れて象牙質が露出し、冷たい飲み物や甘い食べ物で「キーン」とした痛みを感じます。
日本歯科保存学会の調査では、知覚過敏の患者の多くが「ブラッシング圧が200g以上」と報告されています。
エナメル質の摩耗
ホワイトニング歯磨き粉など、研磨剤入りの製品を強い力で毎日使用すると、硬いはずのエナメル質も少しずつ摩耗します。
摩耗は進行しても再生せず、歯の耐久性や美しさを損ないます。
トラブル発生のメカニズム

歯や歯茎は硬くて強いように見えて、実は繊細です。
ブラッシング時にかかる力が大きすぎると、毛先がエナメル質や歯茎に物理的ダメージを与えます。
さらに、酸性飲食物摂取後の柔らかくなった歯面に強い摩擦を加えると、削れやすくなります。
このダメージが毎日繰り返されることで、時間とともに症状が悪化します。
磨きすぎによるトラブルと原因の比較

| トラブル名 | 主な原因 | 主な影響 |
| 歯茎下がり | 強すぎるブラッシング圧、硬い毛の歯ブラシ、横磨き | 知覚過敏、歯根虫歯、見た目の老化感 |
| 楔状欠損 | 横磨き、硬い毛+強い力の組み合わせ | 歯の欠け、痛み、審美性の低下 |
| 知覚過敏 | エナメル質摩耗、象牙質露出 | 冷・熱・甘い刺激での痛み |
| エナメル質摩耗 | 研磨剤入り歯磨き粉の過剰使用、酸性食品摂取後の即時ブラッシング | 虫歯になりやすくなる、歯の黄ばみ悪化 |
「やりすぎ」のサインを見極めるセルフチェック

・歯ブラシの毛先が1か月以内に広がる
・歯茎のラインが下がってきた気がする
・歯と歯茎の境目にくぼみができている
・冷たい飲み物がしみる
・歯の色がまだらになってきた
1つでも当てはまる場合は、磨きすぎの可能性があります。
正しい歯磨きの回数・時間・力加減

・回数:1日2〜3回が目安(食後・就寝前)
・時間:1回3分程度
・力加減:150〜200g(キッチンスケールに歯ブラシを押し当てて確認可能)
・歯ブラシ:やわらかめ〜ふつうの毛質、ヘッドは小さめ
・交換時期:1〜1.5か月
磨きすぎと磨かなすぎの違い

| 項目 | 磨きすぎ | 磨かなすぎ |
| 虫歯リスク | エナメル質摩耗で上昇する場合あり | プラーク残存により高い |
| 歯茎の状態 | 下がる、出血、炎症 | 腫れる、出血、歯周病進行 |
| 見た目 | 欠け、くぼみ、知覚過敏での歯色変化 | 着色汚れ、黄ばみが目立つ |
| 長期的影響 | 修復治療の必要性が出る | 抜歯や入れ歯・インプラントの可能性が高まる |
まとめ

・歯磨きのしすぎは、歯茎下がり・楔状欠損・知覚過敏・エナメル質摩耗を引き起こす
・適切なのは「回数より質」、特にブラッシング圧と方法が重要
・酸性飲食物摂取後は30分空けてから磨く
・気になる症状があれば歯科医院で相談を
「しっかり磨く」ではなく「正しく磨く」ことで、歯と歯茎を一生守ることができます。